「数学Ⅰ」「数学A」の「Ⅰ」や「A」って何?
数学の科目名には「数学Ⅰ」や「数学A」のように,「Ⅰ」「A」「Ⅱ」「B」「Ⅲ」「C」といった記号が付いています.これらの記号はいったい何でしょうか?
この記事では,数学の科目名に関する疑問に答えたいと思います.
目次
Q. どうして「Ⅰ」や「A」に分かれているの?
全ての高校生が,高校数学の全範囲を学習するわけではありません.そのため,目的に合わせて,いくつかの科目に分割されています.例えば「数学Ⅰ」は,中学数学からの関連を考慮しながら,高校生に必須となる数学的素養を身につけられるように内容が定められています12012年度開始の学習指導要領より.
Q. 全部ローマ数字で良いのでは?「A」や「B」を使う意味とは?
「数学A」や「数学B」は,全ての単元を学習する必要がありません.能力・興味・進路などに応じて,学習する単元を選択する事ができます2と言っても大抵の場合,高校側で学習する単元を決めてしまうのですが..「数学Ⅰ」や「数学Ⅱ」では全ての単元を学習するため,こうした性質の違いを表すために,「A」や「B」が使われているのでしょう.
また,なぜ他の記号ではなくローマ字(ラテン文字)が使われているのかと言いますと,かつて存在した科目名「数学ⅡA」「数学ⅡB」の名残りだと考えられます.1956年の学習指導要領で定められた「数学Ⅱ」の内容が広大であったため,実学重視の「数学ⅡA」,進学重視の「数学ⅡB」に科目を分割したという歴史があります.その頃の名残りで,ローマ字が用いられているのでしょう.
Q. 学習する順番は決まっているの?
ローマ数字が付いた科目は,「数学Ⅰ」→「数学Ⅱ」→「数学Ⅲ」の順で学習することが決まっています.
また,「数学A」「数学B」「数学C」は,「数学Ⅰ」の学習を終えていることが,授業を受けるための条件となっています.
多くの進学校では,「数学Ⅰ」→「数学A」→「数学Ⅱ」→「数学B」→「数学Ⅲ」→「数学C」の順に学習するかと思います.
(余談)2022年度開始の学習指導要領
2022年度入学の学生から,学習内容が変わります.
変化内容が気になる方は,以下のリンク先を確認してみてください.
大学受験ハッカーさんや数研出版編集部さんが,とても分かりやすくまとめています.
(余談)学習指導要領について調べたい方へ
最後に,学習指導要領に関する,いくつかのサイトを紹介します.
(参考文献の紹介も兼ねています)
文部科学省の新しい学習指導要領の解説ページ
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1383986.htm
国立教育政策研究所の学習指導要領データベース
https://erid.nier.go.jp/guideline.html
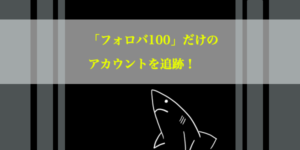

中2なりたてです。先輩に勧められて中3が終わるまでに数Ⅲ以外を終わらせるという目標を立てたのですが、そもそも数Ⅰやら数Ⅱやらが分からなかったのでとても参考になりました。ありがとうございました。